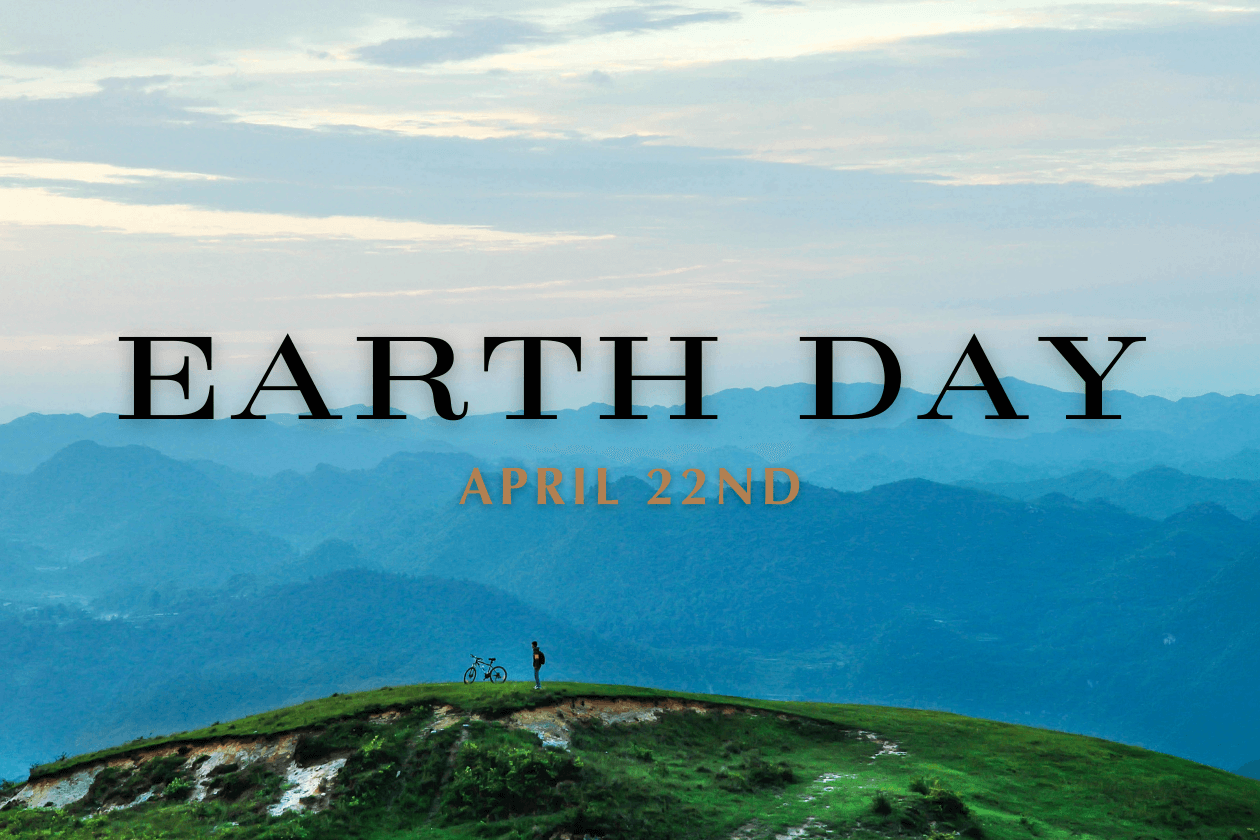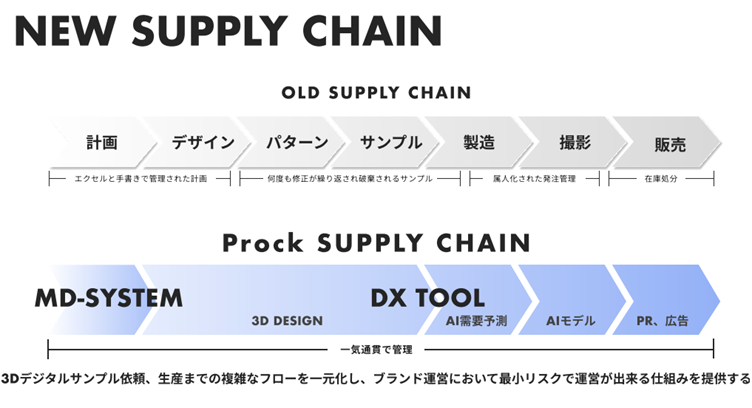サスティナブルシーフード|問題と企業の取り組み、提供するレストランを紹介

現在、世界の漁業のおよそ3分の1が、持続不可能なかたちで行われていることをご存知でしょうか?
このままの方法で漁業が進むと、食卓から新鮮な魚が消え、豊かな海も残らないリスクがあります。
その解決策として注目を浴びているのが、「サスティナブルシーフード」の取り組み。持続可能な方法で、魚介類を養殖したり、漁獲したりすることで、これまでと同じように魚を楽しめる生活や、豊かな海を守ることを目指しています。
今回の記事では、サスティナブルな魚介類の判断基準となるマークから、漁業の持続可能性が重要視される理由、そしてサスティナブルシーフードの消費例まで幅広くご紹介します。
最後には、「サスティナブルシーフード」が楽しめるレストランも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
サスティナブルシーフードとは?
サスティナブルシーフードとは、持続可能なかたちで漁獲、または養殖された魚介類のこと。
具体的には、以下の2つの認証のいずれかを取得している水産物のことを指します。
- MSC®認証 :水産資源と環境に配慮しサスティナブルな漁業で獲られた水産物の証
- ASC®認証 :環境と社会への影響を最小限にして育てられた養殖の水産物の証
詳しくは後述しますが、このような認証が必要となったのには、現行の漁業がサスティナブルではないためです。
海洋と魚介類が直面する問題とは
ここまで、認証マークに関してみてきましたが、MSC®認証や、ASC®認証が必要とされるのは、魚介類が私たちの食卓に並ぶまでの過程には、いくつもの課題があります。
ここでは、過剰漁業と、漁業の方法に関して解説します。
過剰漁業の現状
現在、世界の33%もの魚が獲られすぎているのをご存知でしょうか。
獲られすぎているというのは、種が絶滅の危機に瀕する手前の状態になるまで魚介類を獲りすぎているということを意味します。
事実、海洋生物は年々減っており、1970年と比較すると今いる海洋生物は約半分の49%。
このように、過剰漁業を続けることは、海洋生物が減少していくことに直結する問題です。
破壊的な漁業方法
破壊的な漁業とは、毒やダイナマイトを用いた漁業を意味し、まさにサスティナブルではない漁業方法です。
具体的には、シアン化合物の毒で魚を麻痺させたり、ダイナマイトで爆発を起こし魚を水面に浮かせたりして、おこなわれる漁業のことを指します。
破壊的な方法で漁業を続けると、周囲の環境にまで影響を及ぼしますが、いまだにいくつかの国ではおこなわれている漁業方法なので、現在の漁業が抱える問題の1つとされています。
国際社会が取り組む解決策
このような現状に対し、国際社会では認証マークと国際目標を通じてサスティナブルな漁業を目指しています。
それぞれ解説いたします。
2つの認証マーク
サスティナブルな漁業の証、MSC®認証
MSC®認証とは、サスティナブルな漁業で獲られた水産物に与えられる認証。
海洋管理協議会(Marine Stewardship Council®)によって判断される認証マークで、水産物を持続可能なかたちで守っていくことから、『海のエコラベル』とも呼ばれます。
MSC®認証を取得するためには、MSC®漁業認証とCoC認証の2つの基準をクリアする必要があり、取得の水準が比較的厳しい認証です。
CoC認証とは、加工・流通チェーン内でMSC®認証と非認証の水産物を区別するための仕組みのことです。
養殖をサスティナブルにするASC®認証
ASC®認証は、サスティナブルな方法で生産された養殖水産物に付与されるエコラベルです。
水産養殖管理協議会(Aquaculture Stewardship Council®)によって、環境と社会の両方への影響を抑えながら育てられた水産物が選ばれます。
魚の獲りすぎ問題以外にも、養殖場から魚が逃げ出したり、餌によって海洋の生態系が変わったり、さまざまにある影響を防ぐためにASC®認証は必要とされています。
SDGsゴール14『海の豊かさを守ろう』
SDGs(持続可能な開発目標)は、国連が2030年までに達成すべきと提唱する17の開発目標で、サスティナブルシーフードに関連するのは、SDGsゴール14『海の豊かさを守ろう』です。
持続可能な漁業や養殖を重視するため、ゴール14は具体的に以下のようなターゲットを設けています。
- 海洋汚染を改善すること
- 海洋の生態系を保全し、回復すること
- 海洋酸性化を防ぐこと
- 持続可能な漁業をおこなうこと
- 海岸や海洋を維持すること
- 過剰漁業に繋がる漁業補助金を禁止・抑制すること
- 持続的な海洋資源からの経済利益を増加させること
- 持続的な海洋環境のため、科学知識や調査、技術を増やすこと
- 小規模漁業従事者を支援すること
- 国際海洋法を施行し、強化すること
ゴール14のターゲットは、いずれも漁業や海洋にまつわる課題を解決する内容を含んでおり、国際社会でも大きな影響力をもつ国連がメインとして動くことで、サスティナブルシーフードの重要性が目立ってきています。
SDGsに関して、より詳しい情報が知りたいという方は、下記の記事にどうぞ。
SDGs(持続可能な開発目標)の詳細記事
サスティナブルシーフードを盛り上げる国内企業
国際社会の取り組み以外にも、さまざまな動きで社会に広がるサスティナブルシーフード。まず、国内企業がどのようにサスティナブルシーフードを導入し、市場を盛り上げているのか説明いたします。
大きくわけ、サスティナブルシーフードを市場に出回らせる役割を担う企業と、社員食堂でサスティナブルシーフードを積極的に消費する企業の事例を集めました。
and BLUE
and BLUEは、サスティナブルシーフードがより多くの食卓やレストランに並ぶよう、日本社会に広げる役割を担っている企業。
具体的にsnd BLUEは、下記のような活動をおこなっています。
サスティナブルシーフード(*MSC/ASC認証水産物)の紹介
サスティナブルシーフードを扱う為に必要なCoC認証の取得サポート
サスティナブルシーフードを使った日本で唯一のケータリングを運営
このように、国内でもっとサスティナブルシーフードが当たり前になるよう、活動をおこなっている企業です。
パナソニック
パナソニックは、社員食堂にてサスティナブルシーフードを使ったメニューを提供しています。通称『サスシー』で社員に浸透しているサスティナブルシーフードは、本社において選択率が常に30%超えの人気メニューだそうです。
同社は、全国すべての社員食堂にてサスティナブルシーフードの普及を目指しており、今後も期待が高まります。
MS&ADインシュアランスグループ
パナソニックに続き、MS&ADインシュアランスグループも社員食堂にてサスティナブルシーフードを導入する企業の1つ。
あまり身近ではないサスティナブルシーフードであったと思いますが、初の『サスティナブル・シーフードデー』では、長蛇の列ができ、平均の売上と比べ40%増の大盛況だったそうです。
このように、特別なレストランや販売店を選ばなくても、社員食堂という身近な場所で持続可能な魚介類を楽しめる取り組みが増えています。
では、導入している企業以外に、日常の生活のなかではどのようにサスティナブルシーフードを消費できるのか、最後にご紹介いたします。
サスティナブルシーフードを楽しめる場所
魚介類を消費しながら、サスティナブルな海を未来に渡せる消費例があります。
日常でできる消費の例とし、サスティナブルシーフードに出会えるレストランや、スーパーで手に入る魚介類メーカーブランドをご紹介いたします。
持続可能な魚類を楽しめるシンシアブルー
サスティナブルシーフードを積極的にメニューに取り入れているレストランをご紹介いたします。
シンシアブルーは「100年経っても豊かな海を」をテーマとするレストラン。店舗で使う魚介類は、MSC/ASC認証を取得した漁業、または漁業の持続可能性を高めるプロジェクトに取り組む生産者から調達しています。
シンシアブルーのシェフ、石井さんにはサスティナブルシーフードを提供することが、「消費者にとって持続可能な未来を考えることになれば」という想いがあるそう。
スタイリッシュでおしゃれな空間で、見た目も味も美しい料理を通し、海の持続性を考える時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
サスティナブルシーフードを購入するなら
自宅でサスティナブルシーフードを楽しみたい方のために、スーパーなどで手に入る商品をご紹介いたします。
サスティナブルシーフードを使った冷凍食品などを開発・販売しているメーカーやブランドは以下の通り。
- グリーン・アイ natural(イオングループ)
- マルハニチロ
- ニッスイ
お家でも気軽にサスティナブルな食材を楽しめるので、ぜひ購入してみてください。
さいごに。水産資源を守りながら、魚介類を楽しもう
先ほども述べましたが、日本は国際的に見て魚介類の消費量が多い国のひとつ。
海の恩恵を受けながら、食生活を楽しんでいる私たちだからこそ、海洋や水産物の未来を考えながら持続可能な消費をしていくべきだと思います。
サスティナブルシーフードは、今でこそ見かける機会があまりないかもしれませんが、日常のなかでアンテナを高く張って探してみると、意外と身近にあるかもしれません。
ぜひ、サスティナブルな食材を消費してみる気軽な社会貢献に参加してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【免責事項】
※本記事に掲載の情報は、公的機関の情報に基づき可能な限り正確な情報を掲載しておりますが、情報の更新等により最新情報と異なる場合があります。※本記事はエシカルな情報提供を目的としており、本記事内で紹介されている商品・サービス等の契約締結における代理や媒介、斡旋をするものではありません。また、商品・サービス等の成果を保証するものでもございません